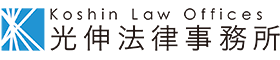共同親権(2)
1 未成年者に対する離婚後の共同親権制については、民法の改正点の概要について昨年のブログで述べましたので、今回は、単独親権制と共同親権制とでどう違ってくるのかについて考えてみましょう。
2 民法の改正で、離婚後は父母の一方だけに親権があると定められていた規定が、父母の離婚後もその双方を親権者とすることができることになりました(選択できる。改正民法819条、2024年5月改正、2026年5月施行)。
単独親権の場合は、離婚後は父母のどちらか一方に親権者を指定しなければならず、これを決めないと離婚届も受け付けてくれません。そうすると、父親も母親も親権を譲らず、話し合いで解決できなければ調停や裁判で離婚に決着が着くまで親権の行方も時間を要してしまいます。これでは子にとって大変に不安定で心身ともに悪影響があると言えます。
改正法では、成年に達しない子がいる場合に親権について合意がととのわない時でも、親権者の指定を求める家事審判または家事調停の申立てがされている場合には離婚届けは受理されます(765条1項2号)。
3 日本の場合、2020年の「人口動態調査」によると妻が親権を持つケースが80%を超えているようです。当事務所で実際に担当したケースでも、母親側が子どもを連れて夫と別居することが多く、そうなると、父親側は子供に会えないケースが多くありました。これは離婚後も同じで、親権は母親側に認められるケースが多いのです(それは、どうしても「母性優位」が原則であり、子の心身の安定を考慮すると「現状維持」、すなわち子を連れて家を出た母親と子との生活の現状を動かす必要性は認められないことが多いということです)。
そして、親権を妻側がとると、父親は子に会いにくくなる、特に母親は夫を子に会わせようとしないことが多い。したがって、養育費の支払いも滞りがちとなるということに繋がりやすくなります。
それが、離婚後も父親が共同親権を持てるとなると、子どもとの交流も積極的に行えるようになり、それが、養育費不払いの問題を改善する方向に向きやすくなると言えるのではないでしょうか。もちろん、養育費の支払いと面会交流とは関係がなく、面会交流ができてもできなくても養育費は支払うべきものです。また、養育費を支払わないから面会交流をさせないと言えるものでもありません。しかし、子になかなか会えないとなると、子に対する関心も子の養育への気持ちも萎えがちになるのではないでしょうか。
4 共同親権のもとでは、進学、転居、手術など、子どもに関する重要な決定を行う場合には、父母双方の合意を要するとするのが原則であり、合意できない時には家庭裁判所が判断します。ただ、ここで問題となるのは、妻側が二度とこの男とは会いたくない、感情的にも生理的にも受け付けないということがあり得ます。とりわけDVが問題となったケースやモラルハラースメントのケースなどは考えなければならないことが多いと言えます。
モラハラの場合、妻のことをあらゆる手段で支配するというのがその本質ですので、離婚後も、親権の行使を手段として、様々なことを仕掛けてくることが考えられます。養育費の支払いや、面会交流のやり方についての話などを手段として、近づいてくることが予想されます。このような相手とは、離婚の際に共同親権とすることを断固拒否する必要があります。ただ、相手方は、婚姻中の暴力等のDVを否認し、共同親権を求めてくるでしょう。そこで家庭裁判所が判断することになります。その際、裁判所は、「子の利益ため」、「父母と子との関係」、「父と母との関係」、「その他一切の事情」を考慮します。とりわけ、①父または母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき、②父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれの有無などについて検討することになっています。しかし、巧妙に虚偽を述べて裁判所を騙そうとする人間がいます。様々な嘘をつきながら、何としても妻に対する支配を及ぼそうとして、「共同親権に応じない限り離婚はしない」と主張しだすこともあり得ます。
裁判官の眼力が問われる状況が多々出てくると思われますが、このような男性を相手とする場合には、とにかく離婚の手続きをとる前に、モラハラやDVの客観的証拠を保存しておくことが重要です。例えば、暴行の写真、青あざや傷あと、診断書、相手の音声、メール等々です。
5 なお、新法が施行されれば、今後、様々な問題が出てくると思いますが、すでに離婚している人も、単独親権を共同親権に変更することを求めることができるようになります。