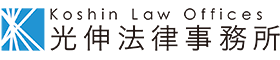職場におけるハラスメントとは?
1 ハラスメント(嫌がらせ、いじめ)という言葉は、近時、頻繁に使われるようになってきました。その種類は多岐にわたりますが、法律が特に職場におけるハラスメントとして定めているものがあります。事業主はこれらを注意しておく必要があります。
これを類型に分けると4つあります。それは、
⑴ パワーハラスメント(パワハラ)
→労働施策総合推進法第30条の2
⑵ セクシャルハラスメント(セクハラ)
→男女雇用機会均等法第11条
⑶ 妊娠・出産等に関するハラスメント(マタニティハラ・マタハラ)
→男女雇用機会均等法第11条の3
⑷ 育児・介護休業等に関するハラスメント(ケアハラ)
→育児・介護休業法第25条
の4類型になります。
そして、これらを実効的に運用するための指針も定められています。
2 措置を講じる義務と責務
上記の法律はいずれもそれぞれのハラスメントの内容を定めるとともに、事業主に雇用管理上の措置を講じる義務と責務を課していて、条文はほぼ共通しています。
⑴ 事業主に対するもの
共通して①から③の対応を求めています。
① 予防から相談対応・再発防止に関する措置義務
② 相談をしたこと等による不利益取扱禁止
③ 研修の実施についての努力義務
- なお、セクハラについては、これらとは別に自分の会社の社員が、取引先など他社の社員にセクハラ行為をしたときに、相手の会社から調査を求められたときは協力することを求められます。
⑵ 役員、労働者に対するもの
共通して①から③の努力義務を定めています。
① 関心と理解を深めることについての努力義務
② 言動に必要な注意を払うことについての努力義務
③ 労働者が事業主の措置に協力する努力義務
3 具体的な内容については、1回では書ききれませんので、今後、ハラスメントについての内容や措置等について継続的に記事を書いていこうと思います。